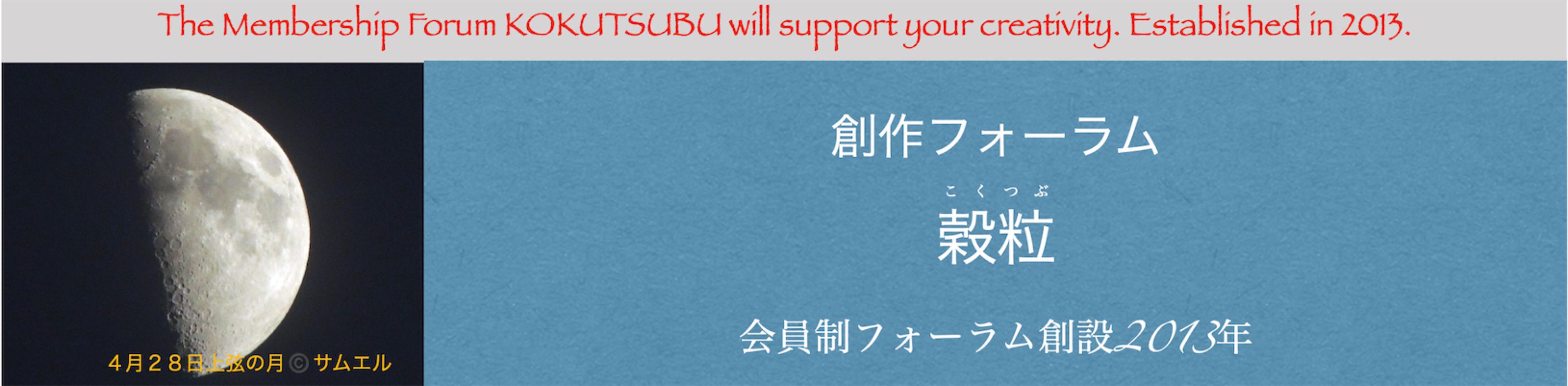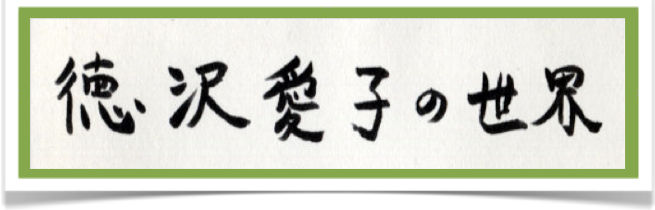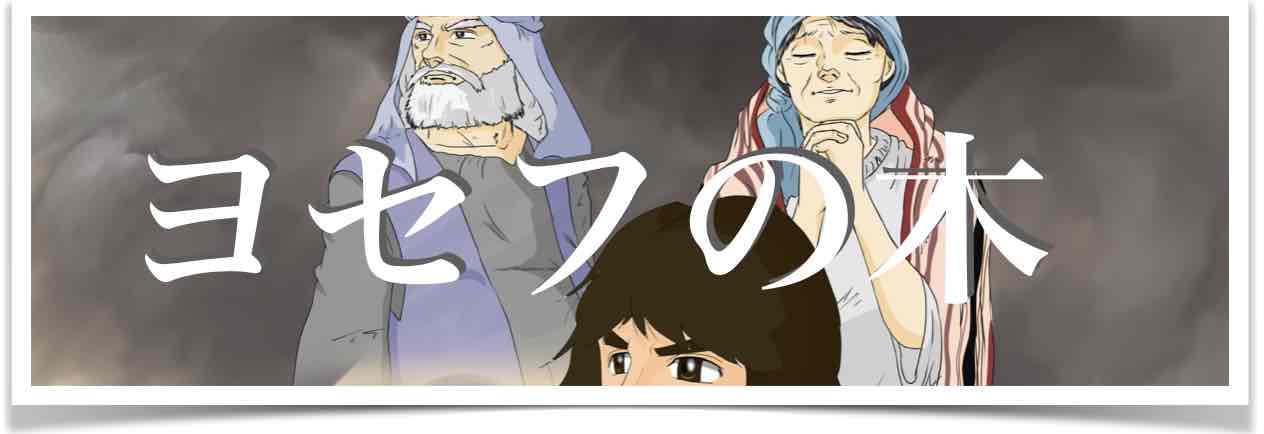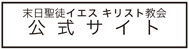20020802中谷 泰士
2020.02.08 評論・研究論文「方言の周辺」投稿者:中谷 泰士
『咲うていくまいか』新・北陸現代詩人シリーズ 徳沢愛子金沢方言詩集II
詩人の声や姿が濃く言葉に表れる詩に方言をさらに加えたところが、この詩集の批評点だろう。加わったというのは標準語に方言が付け足されたのではなく、方言という言葉の持つ滋味が詩に何らかの拡張的な部分をもたらしているという意味である。その是非や効果、意義に批評的な部分が成立する。単に、方言が面白いというような視点だけでは足りない気がする。
そんなことを考えながら、この詩集を読み手はどのように読むのかと考えてみる。詩を書く当人の日常を連想させるに留まっているとしたら、詩人の伝えたいことは自己完結に終わってしまうかもしれない。それとも、単に珍しいというだけで完結してしまうのだろうか。ここにやはり方言という表現のあり方が浮上してくる。
まず方言は話し言葉であり、書き言葉ではない点を指摘したい。作品は「書かれた方言」であり、日常的な会話とは別な次元の話語とみていいと思う。次に方言は時代の推移の中にあって、消えていく言語であること。失われるという基盤があるゆえに、方言を用いた詩の主題の方向性は、限定されることが実は起こりえる。さらに、詩の扱う主題と方言のかかわりも見逃せない。自然、信仰、歴史、自分史と詩の中の方言の関わりは、それぞれの主題ごとの様相を表わすが、それぞれが効果的か否かという課題もある。ただ詩集全体としては、主題が乱反射しつつも、方言を用いている一点でこの詩集は詩集としての価値を維持していることは否定できない。これらの点で、詩集への批評の物言いができると思う。
方言の使用場面が会話だとすると、詩中の方言は誰を相手としているのか。おそらくは読み手に伝えようとしているのではなく、自己に向き合う対話ではないだろうか。「春一番が吹く/ 樹がおおどに声あげる/ 枯草ががんこにしなる/ 明るい窓が/ どくしょな声//わてはながしまいで/ 春菊をゆでる/ やらこい湯気あび/青々と//じきに うるしい春がくる」(「春一番」) というさりげない詩は、誰かに伝えるためではなく、方言の使い手の自分自身に向けられた独白ともいえる。方言を知るとは、風土や生活を知っていることにつながる。湿った冬の終わりを告げる春一番、「ながしまい」という住居のほの暗いひと隅は、北陸人として自らの人生に向けた繰り言である。
詩の方言を知ることで、使い手の生活や人生にまで読み手の視野は拡張される。一方、その言語は失われることを前提としていることにより、使い手自身の言葉も失われることを暗示し、選ばれる主題もここに隣接する。意外かもしれないが、方言詩は温かな人間の繋がりを示すより死や老い、自然の無残さと妙な親和性をより持っている。方言の使用は、ほのぼのとした情感ばかりを意味しない。方言は、そのネガティブな区域で言語的なメタファーとなる。たとえば、「おじいちゃんのもんを/こわごわつまみだします」(「おじいちゃんのもん」)と始まる詩は「麦茶の道/味噌汁の道/命を養う通り道/透明なガラスの溲瓶にそっと寝かすと/仮死した雀のかたち/その先っちょから ゆらゆうら/ガラスにうす黄色の花模様/それは雀が見る短い夢に似とります」と老人の年老いた陰茎と人生を重ね、詩の流れのままに「勇ましいらと囀ったあの眩しい朝なんか/すっぺらかんと忘れてしもて」と続く。「すっぺらかん」という滑稽な響き言葉が、老いと親和して諦めとも肯定とも、さらに否定とも理解できる重層的な響きをもたらしている。「すっかり忘れてしまって」と表現された場合と比べると、方言が単にユーモラスな表現にとどまらないことがわかる。
さらに、自分自身に対しても「夜さりの底に/青梨ひとつ置いたさいにゃ/深閑として 引戸/その隙間から/たんまっし という死者の眼/ちびたい息 吹きかかるこの静けさ//柱時計二時を打つ」(「静けさ」)と死者の域と現世のあわいを繋ぐ方言が、不思議に吸引力を持ってくる。「たんまっし」つまり「食べなさい」と語りかけられて、生きているかどうか定かでなくなる言葉ではないか。
難しいのは、たとえば方言と歴史をつなぐ場合である。抑圧された民衆の歴史として方言を交え表現しようとするとき、ネガティブな事実がすでに強烈であるために、方言の重層的な味わいがシンクロしすぎる場合があるかもしれない。または親しい人の死を直接主題とすると、死という事実の内にあって、方言はその親和性をうまく調整できない場合もあるように思う。さらに信仰の主題が強烈な場合もそうである。方言を詩に用いるには「さりげなく」まさしく「書かれた話語」として使うのが効果的なのかもしれないと思ったりもする。
最後にこの詩集の詩中のいわゆる「不適切表現」について触れる。結論めくが、差別的表現は方言と親和性が強いことはいうまでもない。しかし反面、人権の意識が低いゆえに「不適切」な方言を用いたとみなすのは違う。もしそう読んだ人がいるなら文学を論じる意味が消失することを自覚してよい。差別とみなされる表現の価値を過大にも過小にも扱ってはいけない。その言葉を用いたことは本人の責と片付けるのではなく、かって使っていた私たちの生活時間の記録としてありのままを私たちすべてが負うべきであるとともに、その情緒を再び味わい尽くすべきなのだ。方言とともに消え去ることを容認していない点で、その言葉遣いを支持したい。