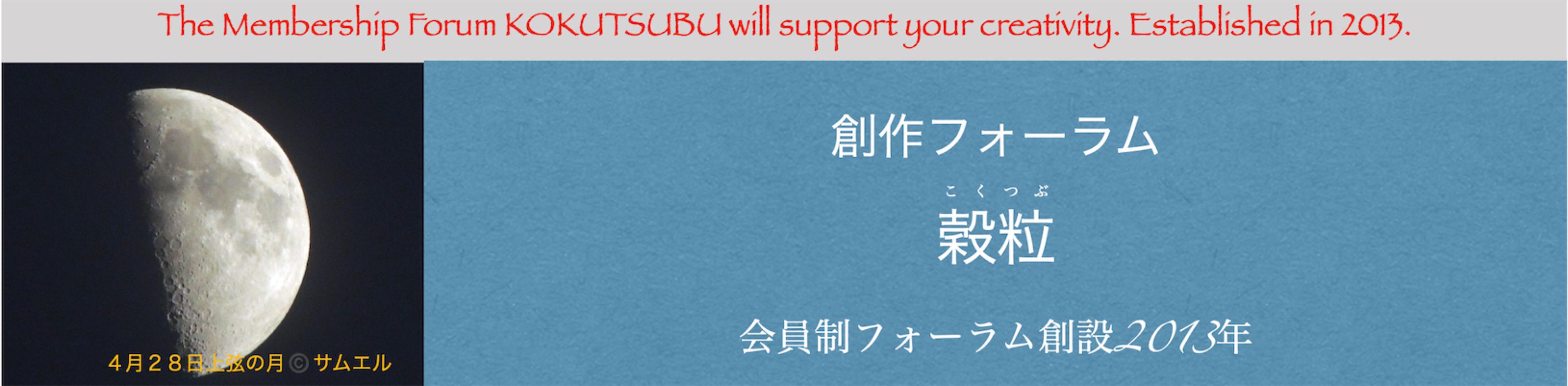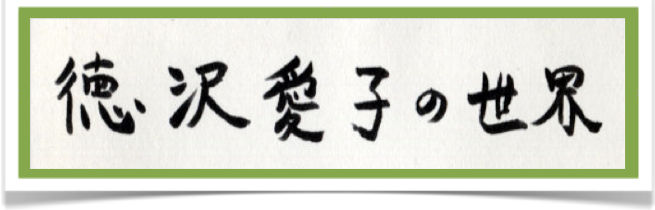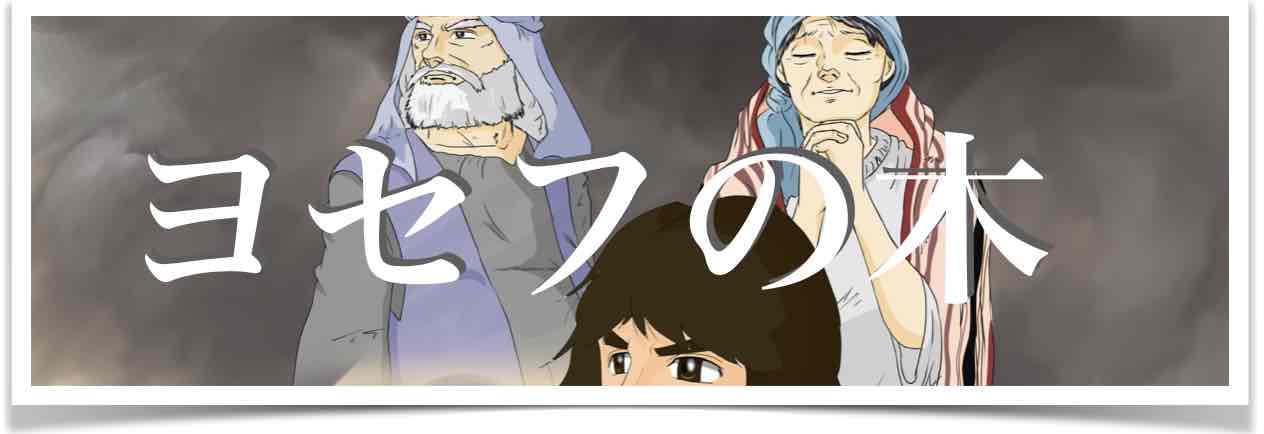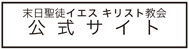23060101田中 健太郎
2023.06.01 評論・研究論文「徳澤愛子詩集『ごんだ餅の人々』を読む」 投稿者:田中 健太郎
ー「あわてかやって」やがて「いんぎらっと」
徳沢愛子の最新詩集『ごんだ餅の人々』(2022、能登印刷出版部)は「新北陸現代詩人シリーズ」として出版されている。詩集タイトルよりも大きく、「金沢方言詩集三」と表示されているが、徳沢愛子がこれまでに出版した四冊の詩集すべてに「金沢方言詩集」と銘打たれており、さらに『はないちもんめ―金沢方言ことば遊びとエッセイ』もあり、詩人の金沢言葉に対する一途な使命感が感じられる。まず一篇の作品を紹介したい。
桃色の湯舟の中で
大桜の下
風が三つ四つ花びらを流す午後
蒸し饅頭のようなほうべた(頬)のたんちが
水色の乳母車の中で眠っている
桜色の優しい時間
寝息も立てず
たんち(幼な子)は桜色の夢を見ている
時々 睫毛が震えているもの
きっと きっと 花の香りに
驚いているにちがいない
あれっ 今 笑ろうた
あれはむし笑い
眠りの澄んだ上澄みにいて
桜に頬ずりされている
青い宇宙と 桜色の大地
往ったり 来たり
たんちは夢の高見で
世界はこんなにも素敵と
がんこに叫んでいる
ここに夢見るたんちがいる限り
老いたわて(私)は まだ生きられる
同じ夢の湯舟で
たんちよ 未来よ
美しくあれと祈るわては
今 桜色の溢れる湯舟から
出られないでいる(全篇)
満開の桜の下、乳母車で眠っている幼な子=「たんち」が夢見ている姿を「桜色の湯舟」の中にいると喩えている。その安心感。最も美しいものが、最も美しい季節におかれている夢見心地。これを表すのに、「ほおべた」「がんこに」という金沢方言の語彙こそがふさわしいと感じさせられる。幼児はむき出しの存在感。ただそこに存在するだけで、「世界はこんなにも素敵」と叫ぶことができる。その姿を見て「老いたわては まだ生きられる」と感じとった詩人は「桜色の溢れる湯舟から/出られないでいる」と自分自身をも温かい世界に包まれたものとして再発見している。詩人が「美しくあれ」と祈っている未来は、幼子だけのものではなく、そこにしっかり詩人自身も存在しているのである。
いつんまにやら(いつの間にか)
あんさはいっちょまえ(一人前)になった
と書き出された「卒業式」はすべて平仮名で書かれていている。卒業する息子が背広を着てあごにひげをはやしているとされているので、まちがえなく大学の卒業式なのであろう。学長の祝辞を聞く息子の横顔には英知の源からとどいた光が宿っている。
もう あんさは
わてからすだってしもた
もう しゃかいのこ
にほんのこ
せかいのこ
うちゅうのこ
立派に育てあげた息子を、いつまでも手元に置こうとするのではなく、社会に、世界に旅経たせようとして、母親である自分は誇り高く、透明人間に徹しようとしている。
「真理を」は短編であるが「詩という小粒の真珠が/心の地底で小声で歌うている」と、徳沢愛子の詩に対する想いが良く表された作品である。「白い紙の上に緑の鉛筆」で言葉を書き始める。
聖められた言葉は真珠を目指して
この地底を降りていく
さらなる聖めのそよ風を受けながら
きなるい(うらやましい)心もなく すんずらと(すずしげに)
そのとき、詩人の耳には何か「完全なもん」が届いて、耳を研ぎ澄ましていく。徳沢にとって詩とは、聴覚の浄化なのである。清められた耳が、風土にふさわしい土地のことばを掬い上げている。
玉音放送 終戦
真夏日 正午の静寂
単語の羅列によって書き出された「静寂」は続く連でもほとんどが体言止めのブツブツと途切れた、あえて文章としてつながない形で描かれる。兄と姉、後の詩人である妹。この三人が両親から離れた疎開先で「招かざる客」として空腹を抱えて暮らしている。バッタ穫りどじょう掬い、よもぎ摘み。いまだ小学生の三人は食べ物を獲得しようと駆け回る。
食べる 生きる 野を
生きる 食べる 川を
赤目の兄 食事作り ままごと
痩せた姉 手伝う うつけものみたい
笑顔忘れた妹 夕暮れの一本道に
目をこらす すでに異界
ぎりぎり生き延びるために、ひたすら食べ物を集めながら、三人兄弟は「地平線から現れるだろう母親」を「腋臭(わきが)のかざ(におい)する母親」を「骨の髄から待っている」のである。
作品の中では母親との再会が描かれることはなく、読者は母への渇望を抱えたまま放り出される。その頼りなさこそが、少女だった詩人が体験した戦争というものであった。戦争が終わって長い年月を経た今にいたっても、毎年、八月十五日を迎えるたびに、詩人の魂は小学一年生に戻り、「うす闇の小川の水音の中に佇む」のであろう。
お祭りの喧噪の中で、アコーデイオンを奏する傷痍軍人を描いた「堪忍して」も、戦中戦後に少女時代を過ごした詩人の体験に基づいている。
お祭り言うたら
傷痍軍人の心いさぶる(ゆする)軍歌
アコーディオンのギリギリする音律
少女には有り金十円の愛だけ
堪忍して 兵隊さん
片腕の兵隊さん
片足の兵隊さん
片目の兵隊さん
傷痍軍人のアコーディオンの音に心を揺さぶられた「片思いの少女」の手には「お祭りのお小遣い十円札」しか差し出すものがなかった。
緑のお国の大義のため
離れがたい家族のため
君という愛のため
そう叫んで片腕を差し出いた
片足を 片目を
堪忍して 兵隊さん
国を守るためという大義のために体の一部を差し出した元軍人が「洗いざらしの白衣/よれよれの兵隊帽/バッサリ欠けた体」で「涙色の軍歌」を歌って小金を集めている。その姿を見て、なけなしの十円札を投げ出す以外になにもできない少女は、なにも彼女の責任ではないのに「心臓を鷲掴み」にされて、ただ「堪忍して」と繰り返すのである。
「静寂」と「堪忍して」はほのぼのとした作品の多い詩集の中において、異彩を放つ二作であるが、これも徳沢愛子の重要な一面である。
少し涼しくなった夕べ、重い病を抱えたと聞いた知己のことを想う「初秋」。
こうろぎの声と
わての心のあいさ(間)を
冷やっこい風が通っていく
おちょぼ口の秋の風
肩をすぼめた秋の風
うんながら(みなさん)
なんぞげ(自然)に 生きよと
ほれ(それ)にしても
くろなるがん(ゆうがたになるのが)はよなった
末尾四行の金沢方言の響きを堪能する。「けつまづいて つんのめって」「どもこも(どうにも)ならん」と思った時に、詩人はどのように生きてきたか。
おっと そこで下腹に力入れてみる
ぐんと立ってみる
風に向こてみる
額に飛礫(つぶて)受けてみる
筋肉しぼって こらえてみる
「もひとつの力」(第三連部分)
戦後したたかに生きてきた女性の強さが余すところなく描かれる。もとから強かった訳ではなく、生き抜くことで身につけてきた力強さである。その強さは言葉によって支えられてきた。
切れはし一つで
言葉の切れはし一つで
泣いた 吠えた
走った 蹲った
布団かぶった
言葉も 心も 迷走や
おーよしよし 柔らこい言葉
撫で なでの ぬくとい(温かい)手
安上がりで上等の万能薬
副作用なしの治療薬
こんながに(こんなふうに)暮らいとれば
ほら 春風が心こそがいて(くすぐる)いく
世界の涯から涯まで
のんびっと(のんびり)しとるまいか(していましよう)
言葉にわやくちゃ(台なし)にされん
はしかい(利口な)朝がくる
(全篇)
詩を書くような者であるからには、言葉というものに何らかのこだわりを持って生きている。しかし、ときにそのこだわりは「言葉の切れはし一つ」を巡って、あれやこれやと大騒ぎしているだけの「迷走」に過ぎないのではないか。徳沢の目指す言葉は、柔らかく、温かく、ケガや病気を癒す薬のようなもの。そのような言葉と共にのんびりと暮らしていけば、言葉が人生をめちゃくちゃにする悪業ではなく、本当に賢く生きるための智恵に、力になるのではないであろうか。短いながらも徳沢愛子の詩に対する根源的な態度を表した、重要な作品である。
第一章「バラの心」に続く、第二章は「寂光」。同名の作品が章の冒頭に置かれている。「木偶」121号の受贈詩短評」において、同人誌「笛」に掲載された同作の一部を紹介したが、改めて詩集に掲載されたヴァージョンを全篇紹介したい。「笛」掲載時には全篇が標準語で書かれており、それで十分に完結していた作品であるが、
詩集収録に当たって金沢方言による表現が加えられている。
寂光
爺さまの大欠伸は
人を食ってしまいそうだが
ちご(ちがう)ちご とんでもない
残り少ないこの世の気配を
がんこに(いっぱい)吸いこんでおきたいのだ
近頃の奇抜な動画でも
ないナない尽くしの
見たこともない
でかい大穴だ
いち暮れ(早い夕暮れ)の明るい居間で
孫たちのキトキトの笑い声
八角時計の金色の振り子は
調子を合わせる
豆腐の味噌汁のこそばい(くすぐる)匂い
生きてるって叫ぶ大根切る音
麦茶はヤカンの中で
気合の湯気吐く
窓ガラスを震わすすすとい(抜け目ない)風
まっで(まつで)あの祭りの賑わいではないか
家の隙間から
気がねそうに入る蒼い夕暮れ
先の短い爺さまは欲ばすにも(強欲)にも
心の隅にとっときたい(取っておきたい)のだ
今の今しかないと言うふうに
それを片っぱしから
ドンドンピーヒャララの
命張った華やぎにして
何ちゅう(という)見事な大欠伸だろう
何ちゅう見事な祝祭だろう
何ちゅう見事な終活だろう
寂光が
爺さまの深い闇を
その時 照らしたのを
わては(私は)見てしまった
(日本現代詩歌文学館「まつりと詩歌」令和四年三月~五年三月展示)
身近に暮らしている「爺さま」の大きなあくび。不意に出る、大きな口を開けての深呼吸の姿を、おそらく繰り返し見せられた詩人は、爺さまは「残り少ないこの世の気配を/がんこに吸い込んで」おこうとしているのだと受け止めた。自分周りにある、生き生きとしたものを空気と一緒に身体に取り込む。それは詩人自身の願望であろう。「孫たちのキトキトの笑い声」と描かれている「キトキト」は、評者は隣県の富山弁であると思い込んでいたが、金沢でも使用されているのだろう。たとえば市場に並べられた新鮮な魚介類などを表現するのに「キットキト」が使われる。評者が以前勤務していた富山大学では名刺に「きっときとな大学」とのキャッチフレーズが印刷されていたことが思いだされる。老人はそのように若く新鮮なものを、生きているうちに強欲に取り込み、取っておこうとする。それはまだある生を言祝ぐ「祝祭」である。
世の人が「終活」を口にするときに、残された家族に迷惑をかけないように所持品を整理するなど、老人があたかも世の中のお荷物であるかのように語られて、淋しい気持ちにさせられることが多いのだが、とんでもない。今ある生を慈しみ、愛し、これを取り尽くし、味わい尽くそうとすること、それこそが「ドンドンピーヒャララ」の「祝祭」と同義の、本来の「終活」ではないのか。生きることに執着するおおあくびに、詩人は仏教にいう「「仏の真理である静かな智恵の光」である「寂光」を見た。他の作品、「いちくれ時」においても徳沢は「寂光がたった一つの命を包んでいた/今を確かに、手応えあるわての命を/風が吹いていた/なんやかんや(色々と)あるこの世を」と、命を包む「寂光」を描いている。
心は
老いの身を陽に晒せば
心は秋の湖
影 濃くして
湖底に赤い蟹ひそむ
キトキト(新鮮な)の蟹一匹 住まわいて(わせて)
許されるならば
神よ
短詩「心は」もまた、老いることの豊かさを、またその充実した時の長からんことを祈る、詩人の思いが素直に描かれている。さらに、これも短詩である「老いよ 来い」と題された作品においても「老いよ嫌でも応でも/巨像のように 静かに来い」と、老いを積極的なものとして迎え入れる詩人の態度が明らかにされている。
三つ目の章となる「あわてかやって」には金沢方言の音の面白さを最大限に活かした作品が多く収録されている。「いーきの い」では、
いーきな(平気な)顔して 生きまっし
いーかげんで ほんで(それで)いい
いきどうーしい(息苦しい)この世やけど
いごふく(文句)ばかりじゃ
いくしとると(狂っとる)言われっぞ
いちがい(一徹)気ちがいより わけ悪い
いっさいがっさい(全て) 春の水
いっちょうら着て
いっちょまいに(一人前)お任せや
と、「い」の頭韻をふんだんにつかいながら、金沢方言の語彙を駆使している。続く第2連でも
ひとさんあっての わて(私)やがいね
心いっすいで(すすいで)いつんかも(いつも)笑うて
いさどらしい(高慢な)こと 言わんと
いんぎらっと(ゆったりと)生きまいか
金沢ことばの中でも難易度の高いと思われる「いんぎらっと」は詩人の生き方の理想を見事に表す一語であるが、徳沢愛子も最初からそのように生きて来られた訳ではない。章のタイトルともなっている「あわてかやって」は「慌てて」という意味である。
ただ あわてかやって(あわてて)
見合いから二ケ月で結婚し
あわてかやって
五人の息子をバタバタ生み
その心労 疲労回復のてだてとして
あわてかやって 詩を書いてきた
(略)
<奥さん あんたさんは新幹線や
バイクで帰ってきたと思うたら
またバイクで飛び出いていく>
立ち止まって深呼吸もせず
あわてかやって 生きてきた
(略)
でもつらつら振りかえっと
人さんのお役に立とう 立ちたいと
一つの思いできた 気がつけば
その岸辺には小さい花がいつも咲いとった
色とりどりの野花は絶え間なかった
あわてかやることもなく
ほったりした時間を作ってくれていた
いつん時も 忘れんと花たちは
近頃 ふと花の香りが戻る
この鼻ぺちゃ(低い鼻)の上に
あわただしく生きてしまった半生を悔いる。だが、それは人のために役に立とうと急いでいたのだった。
今となって「気がつけば」、その急いでいた日々にも、岸辺には色とりどりの野花が、忘れずに咲いて「ほったりした時間を作ってくれていた」。
ゆるがない芯の強さを持つがゆえの優雅さ。金沢の人たちを表すのには、やはり金沢ことばが最もふさわしいと納得させられる「方言詩集」であった。
いただいたコメントは即座に反映されないことがあります。送信後は30分以上お待ちいただいてからご確認ください。